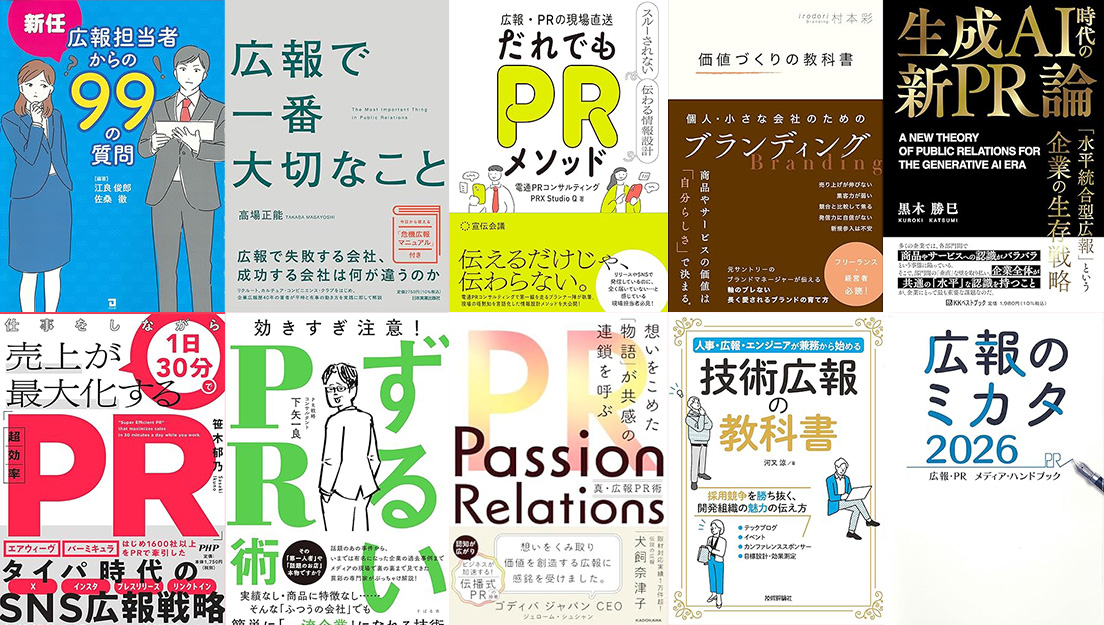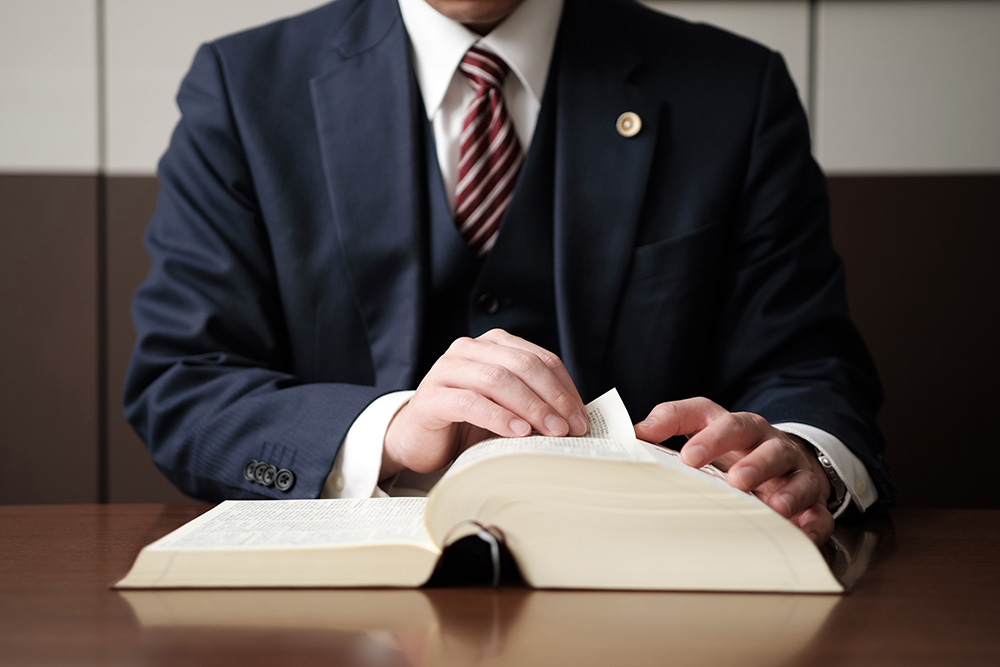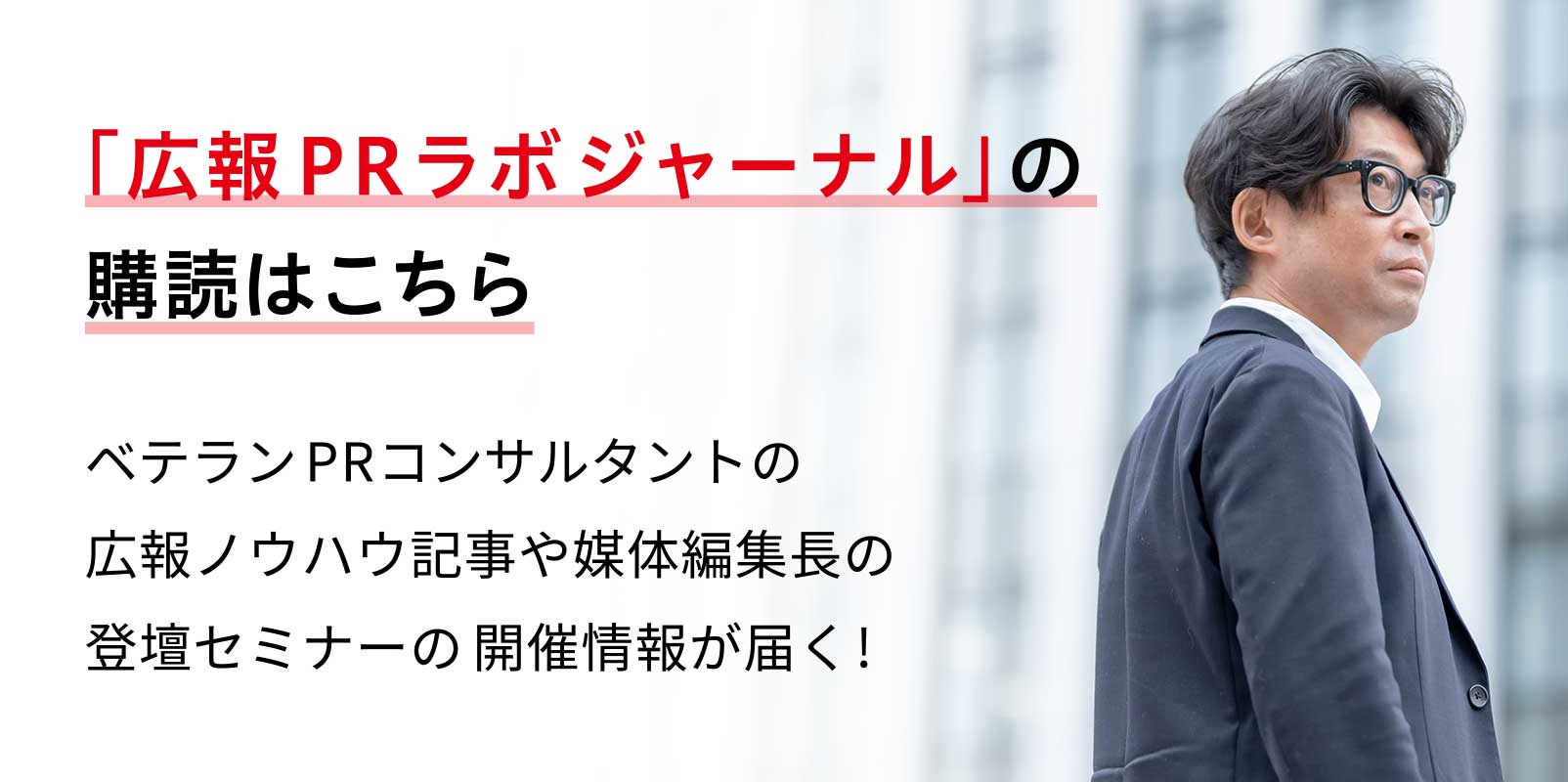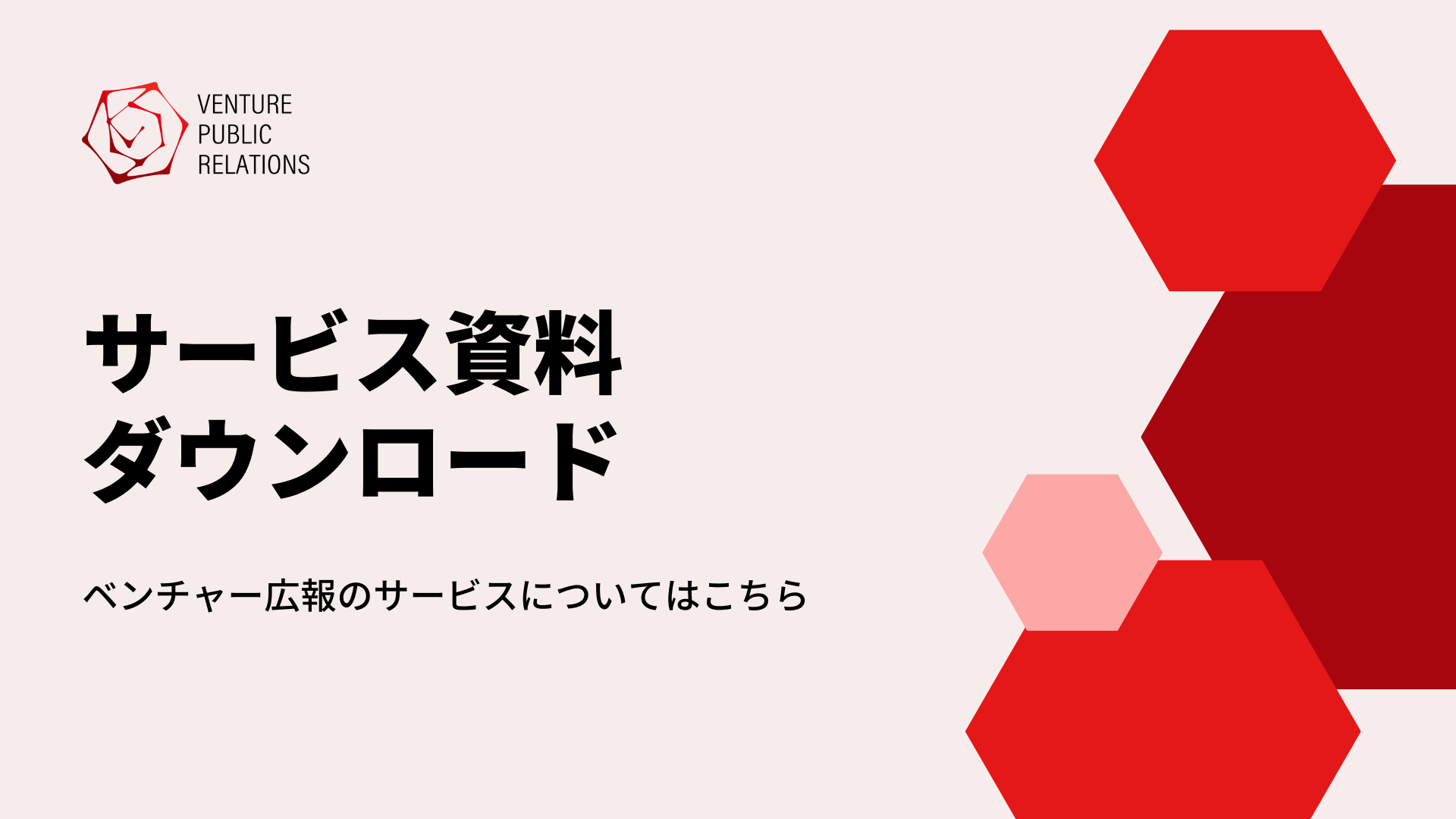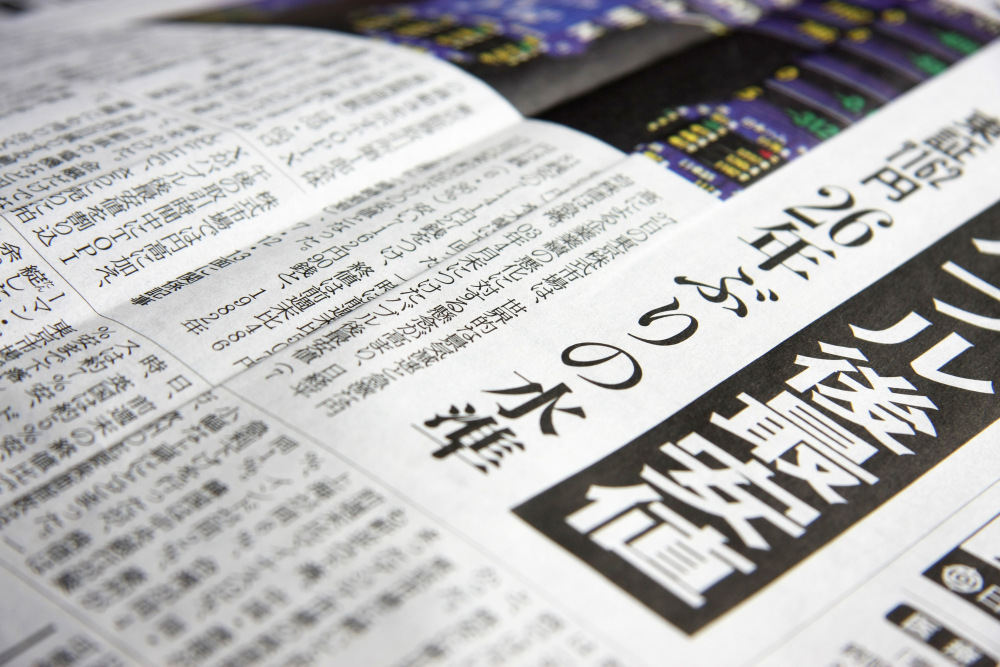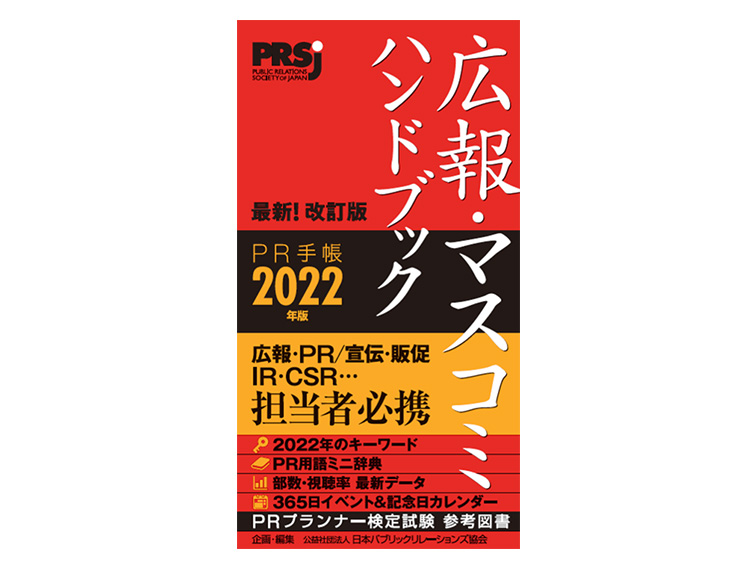スタートアップのためのPR会社
ベンチャー広報の野澤です。
プロ野球の名監督・野村克也(故人)さんは、
「勝ちに不思議の勝ちあり。負けに不思議の負けなし。」
という言葉を好んで使いました。
成功には偶然の要素があり、その要因は実は本人にもわからないことが多い。しかし、失敗には再現性があり、やってはいけない事をすると必ず失敗する。だから、成功よりも失敗からの学びが大きい、という意味です。
僕は、スタートアップ専門のPR会社を15年経営する中で、数多くの会社を見てきました。また、上場企業の役員として、約50のスタートアップへの投資経験もあります。2024年にIPOして、上場の時価総額が1000億を超えたタイミー社も投資先のひとつです。
一方で、成長できずに消えていった投資先もたくさん見てきました。成功するスタートアップと失敗するスタートアップは何が違うのか。過去の失敗事例から学びましょう。
第3位:資金が枯渇
会社の経営では、事業が赤字か黒字か以上に、手元に現金があるかが重要です。お金がなければ、社員の給料も家賃も外注費も払えません。仕入れも借金の返済も金利の支払いもできません。
会社は決算が赤字でも倒産することはありませんが、現金がなくなれば、事業を継続できず、即ゲームオーバーになります。
事業を運営するための現金を、いつのタイミングで、いくらくらい、どう確保するのか。これはスタートアップにとっても最重要課題のひとつです。
創業直後のスタートアップは信用がないので、出資してもらうにせよ、融資を受けるにせよ、普通は、大きな金額を調達できません。最初に用意できる事業資金は数百万円からせいぜい数千万円でしょう。
まずこの現金を使って事業を立ち上げるわけですが、当然、最初は売上ゼロで入金はありませんので、お金は出ていく一方です。通帳の現金残高が日々減っていくプレッシャーと戦いながら、限られた手元資金で一定の成果を出さなくてはなりません。
当初用意した資金で事業を伸ばし、その会社がさらに成長すると証明できれば、追加でお金を出してくれる人が出てきます。例えば、ベンチャーキャピタルとか銀行とかです。
資金調達する→そのお金を使って事業を伸ばす→資金調達する→そのお金を使って事業を伸ばす→資金調達する、、、この繰り返しで、徐々に会社の規模を大きくしていきます。
ただ、スタートアップの失敗の理由に「資金の枯渇」や「資金不足」があげられることが多いですが、これは表面的な理由にすぎません。
なぜなら、事業が伸びていてその会社が将来有望なら、出資者を見つけることはそれほど難しくないからです。たとえ大赤字でも急成長しているスタートアップには、ベンチャーキャピタルや銀行はよろこんでお金を出します。
しかし、逆に、事業成長しなくなった会社は、出資者から見向きもされません。
「お金を投下しても事業が伸びない」
実はこれが、「資金の枯渇」の裏側にある、本質的な失敗理由です。
第2位:商品サービスにニーズがない
顧客ニーズのある商品サービスを作る。そんなの当たり前じゃないかと思われるかもしれませんが、これが結構難しいんですね。
スタートアップの起業家は、自分のミッションやビジョンを重視します。それは、悪いことではありませんが、想いが強すぎるあまり、独りよがりな商品サービスを作って失敗するケースが後をたちません。起業家の思い入れと、顧客ニーズは別問題です。
「素晴らしい製品を開発した」「画期的なサービスを思いついた」という思い込みで、客観的な顧客ニーズをとらえないまま突き進んでしまう。努力しても努力してもユーザーは増えず、売上もあがらず、ある日「顧客ニーズがなかったのだ」と気づく。
これがスタートアップが失敗する典型的なパターンです。
とはいえ、スタートアップの経営者もバカじゃないので、全く顧客ニーズのない商品サービスを作ったりはしません。ここが大事なポイントなのですが、スタートアップの成否を分けるのは、正確にいうと、顧客ニーズの「有無」ではなく「強弱」です。
ビジネスの世界には「ビタミン剤ではなく鎮痛剤を売れ」(Sell painkillers, not vitamins) という格言があります。ビタミン剤というのは「あればうれしいけど、無くても困らないもの」。鎮痛剤は「それがないと困る、いくらお金を払っても欲しいもの」。
つまり「顧客ニーズの弱いものを売ってもうまくいかないよ」という意味です。
未熟なスタートアップは、ビタミン剤レベルの、顧客ニーズの弱い商品サービスを売ろうとして失敗します。良くあるのは、無料のベータ版ではユーザーが集まったけど、有料版にした途端、誰も利用しなくなるというケース。
「お金を払ってでも解決したい」と思うような顧客ニーズ、切実な課題や困りごとを見つけるのは簡単なことではありません。
第1位:社長がポンコツ
社長が優秀なら成功するし、ポンコツなら失敗する。スタートアップは、結局、社長次第です。
だから、僕がスタートアップへの出資を検討するときは、その会社の社長がどういう人物かをじっくり見極めます。人柄やマインドセット、経歴、実績、スキルなど、見るべきポイントは多々ありますが、僕が特に注目するのは、その社長の「問題解決能力」です。
スタートアップは最初に立てた計画通り、スムーズに物事が進むことは100%ありません。プロダクト開発、採用、組織づくり、売上、集客、資金繰り、クレームなど、問題や課題が次から次へとあらわれます。こうした問題と常に向き合い、適切に判断し、課題を解決できる能力が、スタートアップの社長には求められます。
さらに重要なのが「胆力」です。スタートアップの社長は、ハードシングス、答えがない難問や困難に、何度も直面します。
それを乗り越えられる、折れない心、強いメンタルがあるかどうか。どれだけ頭が良くて問題解決能力があっても、胆力がない人は起業家に向いてません。実際、僕は過去に、心を病んでしまう社長をたくさんみてきました。
もうひとつ社長に必要な能力をあげるなら、それは「巻き込み力」です。
スタートアップは社長自身の想いから始まります。「自分の手で世の中を良くしたい」「社会の課題を解決したい」「理想の商品サービスを作りたい」
出発点は”たったひとりの熱狂”です。
最初は手元に何もありません。そこから、資金を集め、経営チームを作り、優秀な人材を採用して、はじめて会社を経営できます。これらの経営資源を集める力が「巻き込み力」です。
「カリスマ経営者」という言葉がありますが、これはスタートアップにも当てはまります。人間的魅力と事業への想いを兼ね備え、社員、顧客、取引先だけでなく、社会全体をも巻き込んで、事業を大きくしていく社長のことです。
最後に
「失敗は悪」ではありません。失敗は貴重な経験です。そして、その経験には学びという価値があります。しかも、その学びは、経験した本人にしか得られない貴重なものです。
スタートアップ先進国のアメリカでは、初めて起業する人よりも、何度も起業してたくさん失敗してきた人に、多くのお金が集まります。経営者としての経験値が高いからです。
アメリカで創業後5年の成長率でトップ0.1%に入ったスタートアップの創業時の社長の平均年齢は45歳というデータがあります。20代30代で会社員をしていたにしろ、起業経験があるにしろ、それまでの多くの失敗経験が40代での成功につながっているのではないでしょうか。
例えば、Uberの共同創業者であるトラビス・カラニックは、Uberで成功する前の10年間は、投資家に騙され、大手企業から訴訟を起こされ、資金調達に奔走し、自分の給料はゼロ、食事はカップラーメンのみという、最悪な時期を過ごしたそうです。
スタートアップは不確実性が高い世界だけに、こうやればうまくいくという、確立された成功モデルはありません。だから、経験に大きな価値があります。中でも、失敗経験は宝です。
スタートアップに挑戦するなら、ぜひ「失敗」をポジティブに捉えてください。