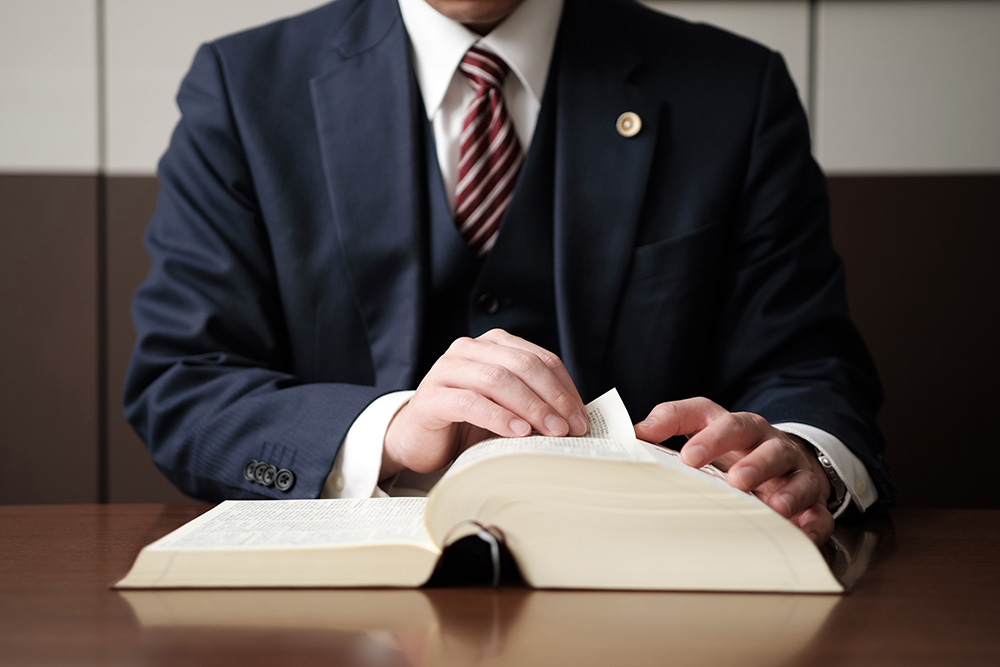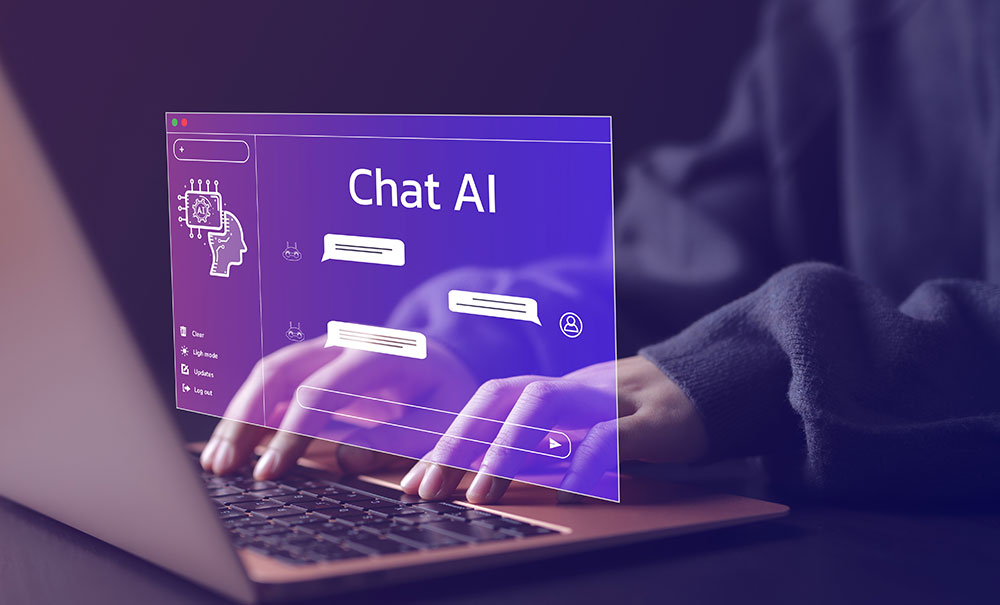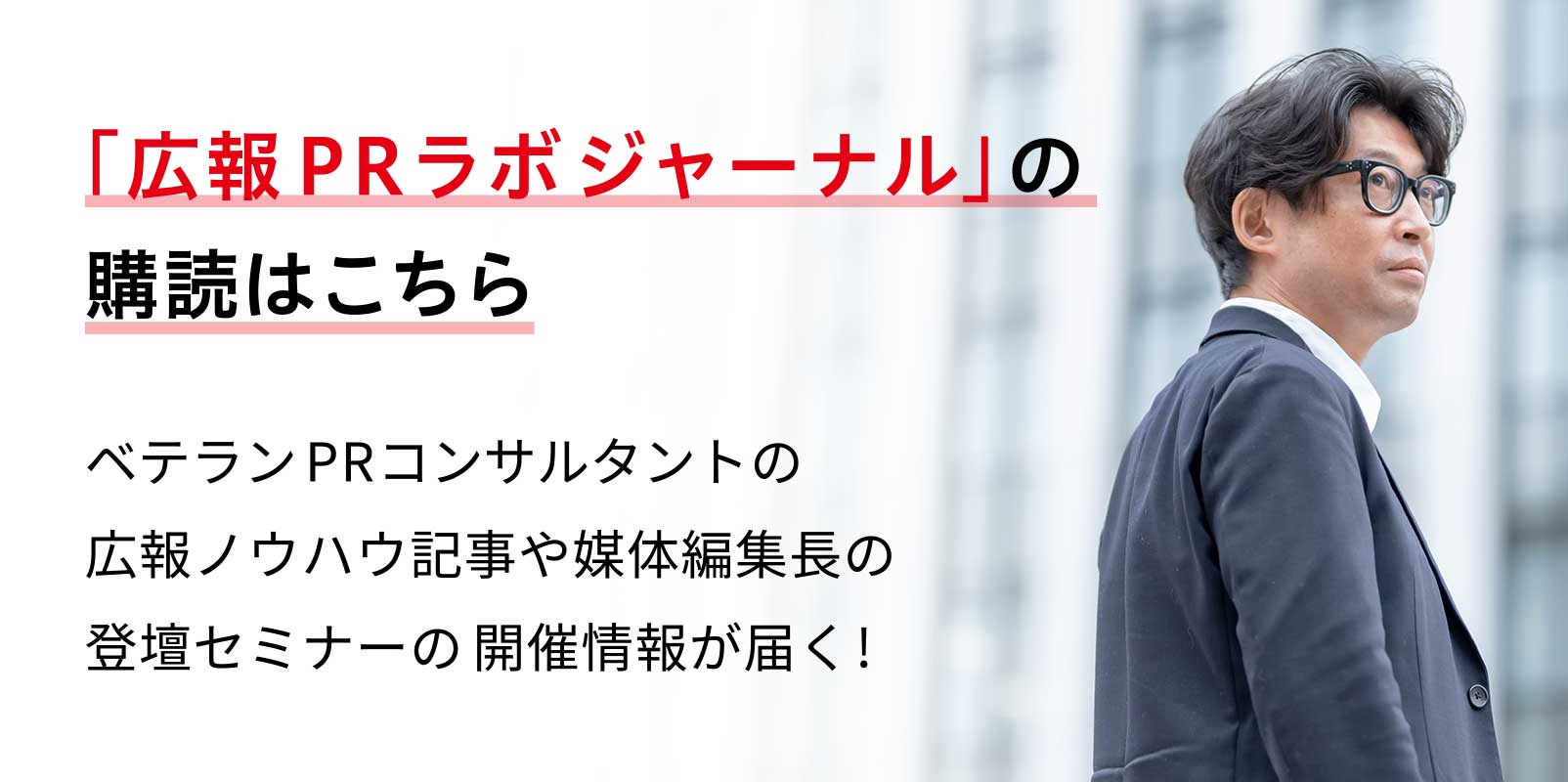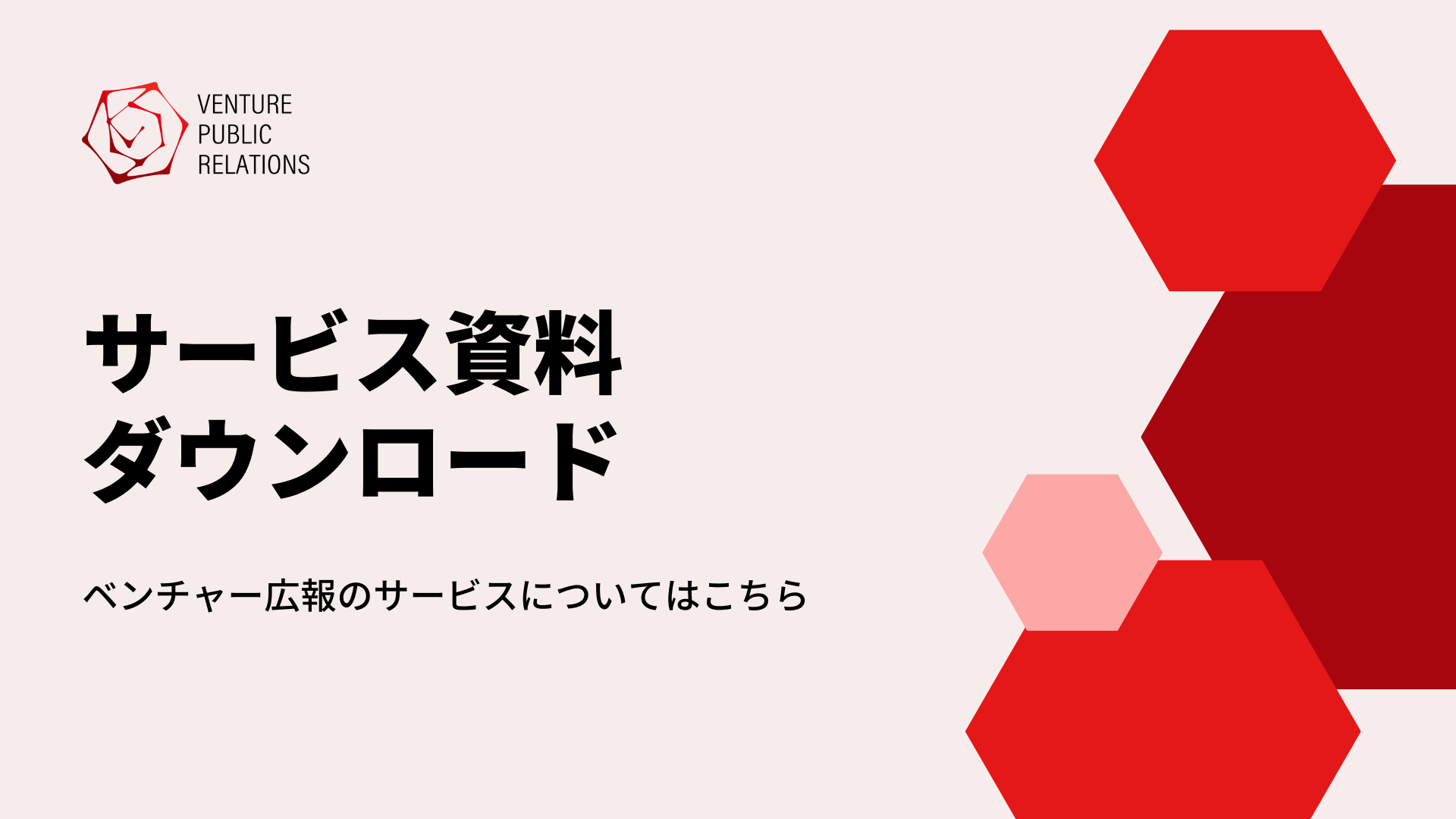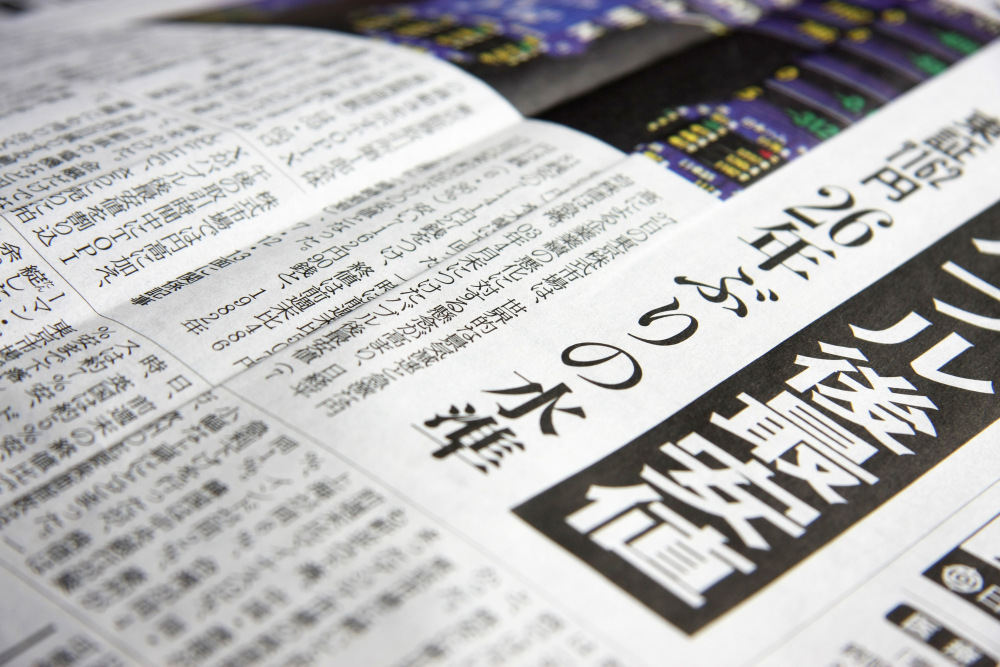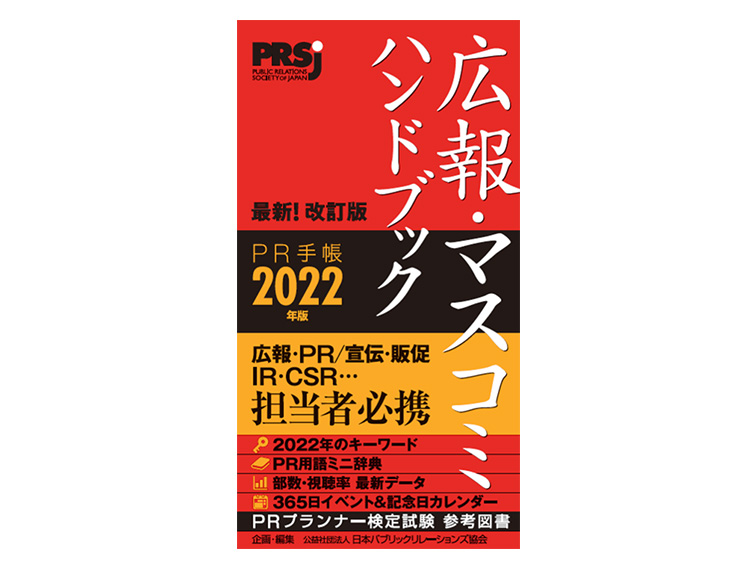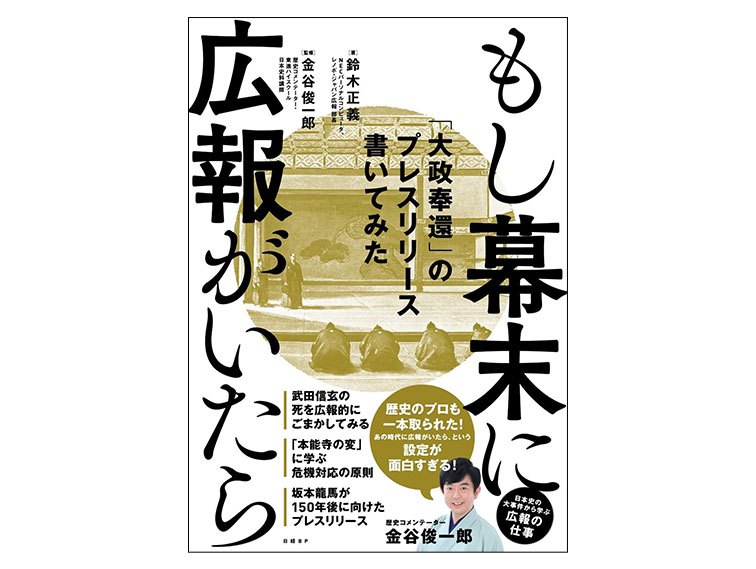スタートアップのためのPR会社
ベンチャー広報の野澤です。
「良いプレスリリース」とは何でしょうか?
僕は、結果的に取材や報道につながったリリースこそが「良いリリース」だと思います。なぜなら、プレスリリースを作成する重要な目的のひとつは、マスコミに報道を促すことだからです。
では、マスコミ関係者が関心を持つプレスリリースはどうしたら書けるのでしょうか。その答えにたどり着く一番の近道は、マスコミの中の人に「どんなリリースだったら読みたくなります?」と聞いてみることです。
今回のブログでは、野澤独自のネットワークで現役または元テレビディレクターの方々にヒアリングを行い、彼ら・彼女らが「こういうプレスリリースなら絶対に見ます」と答えた内容をご紹介します。
ポイントは5つです。
1、瞬間的に中身が分かるもの
テレビディレクターの元には、プレスリリースに限らず、営業関連のものも含めると多くの郵送物が日々届きます。当然、多忙なディレクターたちはその全てに目を通していません。
ただし、机の上の郵送物の束を整理する際に、瞬間的に中身が分かるものは優先的に見ているようです。具体的には、私もよく推奨するのですが、透明の封筒に入ったプレスリリース等がその1つ。
これは、プレスリリースを茶封筒や白封筒といった中身の分からない封筒に入れるのではなく、透明の封筒に入れるという作戦です。実際にテレビディレクターからも「透明の封筒に入ったプレスリリースは見たい・見たくないに関わらず、視界には入る」という声が複数ありました。
ディレクターがここで求めている要素は「瞬間的に中身が分かること」です。つまり、文字が小さすぎて分かりにくい、読みにくいものではなく、タイトルが大きく、何の内容かが瞬間的に分かるような書き方をする必要があります。
2、カラフルなもの
テレビディレクターが日々見ている番組の企画書ってご覧になった事があるでしょうか?その企画書の多くは番組制作会社から提出されたものですが、パンフレットかのようにとてもカラフルなものが多いです。
ディレクターはそういった企画書を毎日見ています。そしてそういうカラフルなものであればあるほど、中身が何か面白いものかもしれないと期待をする傾向があるようです。
ただ、これは先ほどのポイント同様、タイトル等が分かりやすく表示されていて、ディレクター自身も興味を持った場合に限ります。
3、「なぜ今放送する必要があるか?」が書かれているもの
プレスリリースに記載された事実の希少性等も大事ですが、ディレクターにヒアリングした結果浮き彫りになったのは、彼らがもう1つ重要視するのは「なぜ、今放送する必要があるか?」です。
ディレクターによっては事実の希少性よりも「なぜ今?」が合致する事の方が大事だと言い切る人もいました。
その理由は、彼らが上司であるプロデューサーに対して「この企画をやりたい」「この企業を取り上げたい」と上申する際に真っ先に質問されるのがこの「なぜ今?」だからです。
実際にあるディレクターは言っていました。「事実としていくら面白くても、今放送する意味合いが見いだせないものは扱いません」と。
また、こうも言っていました。「事実として面白いプレスリリースがあったとしても、”なぜ今か?”を考えるのが正直かなり面倒くさいです」と。
実際に「なぜ今か?」が丁寧に書かれているプレスリリースってかなり少ないそうです。そんな中で「なぜ今か?」をきちんと明記し、ディレクターがプロデューサーに上申するための手助けをしてくれているプレスリリースは彼らからは確実に好感を持たれます。
4、「他メディアでの掲載事例」が書かれているもの
この掲載事例というのは2つあります。
1つは、そのプレスリリース内容以外で、自社が過去にメディアから取材を受けたという事例。これはディレクターがプロデューサーに上申する際に「過去にこういうメディアからも取り上げられている企業なんで・・・・」という説得材料になります。
もう1つは、そのプレスリリースに書かれている内容で「テレビ以外のメディアで取り上げられている事例」です。例えば新聞・雑誌・Webとかそういうところでもう取り上げられてます、というのは「ニュース内容の価値」として加点になります。
一方、「テレビでどこどこの局に既に取り上げてもらいました」は、逆にマイナスの印象を与えるリスクがあります。
なぜなら、他局の二番煎じはよっぽど社会性のあるニュース以外はやらないのと、彼らも企業に所属するサラリーマンで他局含めて横の繋がりもありますので、パクったパクられたで変な遺恨を残したくない気持ちがあるからなんです。
5、「取材できる人と場所」に関する情報が詳しく書かれているもの
テレビという特質上、映像として成立するかどうかをディレクターは必ず見ます。
なので、実際に取材となった時にどういう役職・キャラクターの人に取材ができるのか?また、どういう場所を取材できるのか?について写真、理想は映像で情報付加されているものは、より検討しやすいようです。
逆に「こういう事実があります」だけのプレスリリースは、彼ら曰く「正直、動きようがない」とのことでした。